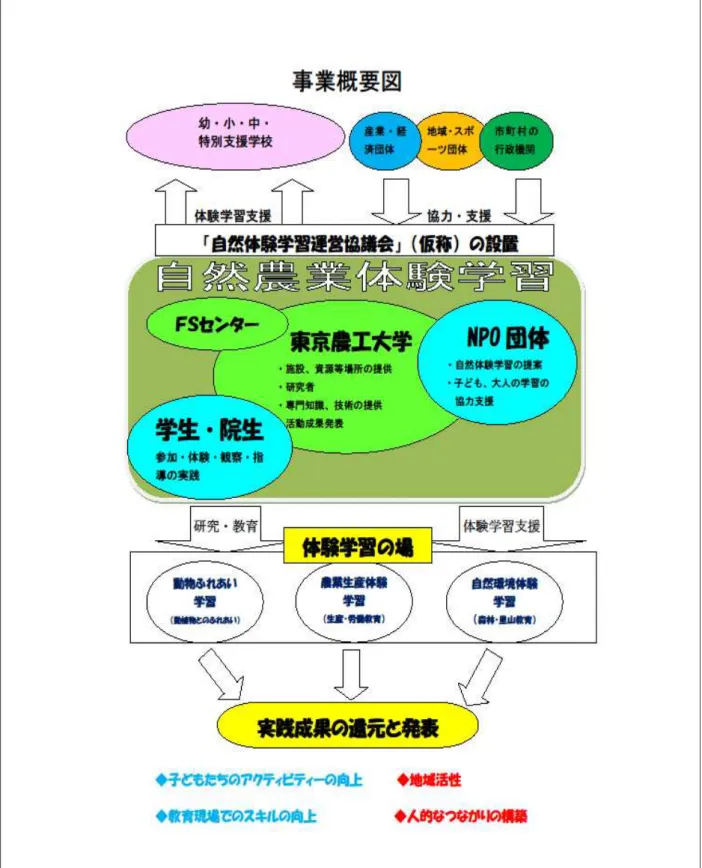「人間主義的地域計画」樹立の一歩を 千賀裕太郎
私は、地域計画学分野の専門家として、主に農山村地域を対象に教育研究活動を行なって きた。私にとっての農山村地域は「学び」の場であると同時に、行政施策・計画策定の場と して、そして地域づくりの支援活動の場として、長くかかわってきた。
そもそも地域の「計画」というのは、地域の現状の「課題」とそこに潜む「可能性」を析出し、 課題の「解決方策」明らかにし、地域のあるべき「将来像」を描くことである、と書くだけ でも、おそらく読者には、「地域の計画」とは、なんと大それたことか、と映ることだろう。 たしかにそれは大それたことではある。「計画」の良し悪しで、地域の未来はまったく異な ってくるのだから。
これまで世間で「地域計画」といえば、都市についても農村についても、まずは「公共基 盤の整備計画」をさすことが多かった。そのことの必要性は一概に否定できないが、あたか も医者が病人に、主として症状を軽くする対症療法を目的とする薬を施用するようなもので、 副作用があったり、病根の除去や体力の回復にはつながらないのと類似している。
こうした地域計画の基底に、大事な理念が欠如してきたのではないか。1980 年代からは、 その「欠如」の一つの部分、例えば「自然保護」は、それなりに対応できるようになってき た。1990 年代に入ると、それがやや拡張されて「(文化的)景観保全」への配慮も、取り 入れられてきた。しかし、「カエル類のビオトープ」などは重視されても「ヒトのビオトープ」 は議論されていないように、いま不足しているのは、「人間」への深い理解に基づく、計画 の基本理念ではないだろうか。
地域計画の分野における人間への関心は、計画主体論という形で、早くから現れてはきた。 そもそも地域計画は「行政計画」の域を出ずに、トップダウン型の策定プロセスが通常だっ たのであるが、一つの傾向として、1980 年代に自然保護への配慮の手続きとして、地域住 民へのアプローチが始まった。しかしながら、人間そのものへの関心、例えば子どもの成長 過程において、地域の自然的・社会的環境の変化はどのような意味を持つのかなどは、地域 の計画に当たってほとんど不問に付されたままである。
私自身、8 年半働いた農水省(行政)から宇都宮大学に移籍したころ(1980 年)から、 この問題に強い関心を抱き続けてきて、啓蒙書(拙著「よみがえれ水辺・里山・田園」岩波 書店)でいくらか論じ、また大学の授業(「自然保護文化論」、「地域社会システム計画論」、「水 資源間理論」など)で講じてきたが、残念ながら昨年 4 月に編集出版した「農村計画学」(朝 倉書店)にほとんど反映することはできなかった。このいわば「人間主義的地域計画」樹立 への着実な一歩を、心ある方々と共に、なんとか始められないかと考えている。ご関心のあ る方にはご連絡いただければ幸いです。
目 次
1 「人間主義的地域計画」樹立の一歩を 千賀裕太郎
3 生物多様性と持続可能性の間
―生活・生産・交換・文化、そして教育の多様性― 鈴木 敏正
37 新たな出発 三島北高での16年 (1966 ~ 82 ) 西岡 昭夫
48 研究ノート・環境教育の射程(4)環境教育の方法—その2— 朝岡 幸彦
54 大学農場施設を活用した「学校と地域の連携」による食育・農業体験学習の展望 と課題 ~東京農工大学農学部教職授業における「農学・環境系ファシリテーター」 の育成と「教職ファーム」の活用にふれつつ~
櫃本真美代・南里悦史・野村卓・二ノ宮リムさち・岩松真紀 ・降旗信一
62 ESD における住民=学習者の主体性と地域開発政策への位置づけ― 「わかりにくい」ESD を乗り越える地域の実践と unlearn とは―
二ノ宮リム さち
71 東日本大震災後の自然体験活動
~福島県猪苗代町の修学旅行等の受入れの現状と風評被害について~研究ノート 中嶋 信
79 災害復興における商店街再生の必要性と ESD 石山 雄貴
87 学校教育は地域の持続可能性にいかに貢献できるのか?
~飯田市竜丘地域における公民館と学校の連携を事例に~ 茹 今
99 被災地における持続可能な農山漁村の地域づくりに向かうリジリアンス(復元力) を高める教育とは~宮城県南三陸町歌津地区をケーススタディとして~
孫 文
108 東京都多摩地区自治体の財政動向について~国分寺市を事例に~ 迫 愛弓
生物多様性と持続可能性の間
——生活・生産・交換・文化、そして教育の多様性—— 鈴木 敏正
はじめに——課題——
2010 年 は 国 際 生 物 多 様 性 年 で あ り、 COP10(名古屋)が開催された。日本では「生 物多様性基本法」(2008 年)を受けて、「生 物多様性国家戦略 2010」が閣議決定され、
「生物多様性保全活動促進法」が制定された。 国際的には、2011 年から「国連生物多様性 の 10 年」が始まっている。この年、東日本 大震災が起こり、「3.11 後社会」が問われて いるという厳しい状勢の中で、生物多様性戦 略を具体化して行くためには多くの困難が予 想される。2012 年の「国連持続可能な開発 会議(リオ+ 20)」の主要テーマは、生物多 様性でも持続可能な開発でもなく、「グリー ン経済」の推進であった。
地球サミット(1992 年)において採択さ れた「生物多様性条約」は、①生物多様性の 保全、②生物多様性の構成要素の持続可能な 利用、そして③遺伝資源の利用から生ずる利 益の公正で衡平な配分を目的としている。し かし、生態・環境問題全体にわたる「先進国 と途上国の対立」がその推進に影を落として きた1。この条約の目的では「遺伝資源の取 得の適当な機会の提供及び関連のある技術の 適当な移転並びに適当な資金給与の方法によ り達成する」(第1条「目的」)とされていた のであるが、とくに③にかかわる利害を強く 持つ有力な当事者であるアメリカが条約未締 結であることは、大きなブレーキになってき た。③の目的の推進のために「遺伝子組み換 え生物」の国際的移動などに制限を加えよう とした「カタルヘナ議定書」(2003 年)にも、 かかわるアメリカ・アルゼンチン・カナダ・ オーストラリア等は未締結となっている。 実際に COP10(名古屋)では、先進諸国
を覆う構造的不況のもとで生物多様性保全 に向けた具体的政策の立ち後れもあって、 2010 年目標は達成できず「失敗」に終わっ たとされ、新たな戦略計画(愛知目標 2011- 2020)が立てられた。「愛知目標」では、① 生物多様性を主流化し、生物多様性損失の根 本原因に対処、②直接的な圧力の減少、持続 可能な利用の促進、③生態系、種および遺伝 子の多様性を守り、生物多様性の状況を改善、
④生物多様性および生態系サービスからの恩 恵の強化、⑤参加型計画立案、知識管理と能 力開発を通じて実施を強化、が戦略目標とし てあげられている。
日本ではその後、東日本大震災後をふまえ つつ、「愛知目標」実現に向けてのロードマッ プを提示した「生物多様性国家戦略 2012- 2020」が閣議決定されている(2012 年 9 月 28 日)。基本戦略としては、これまでの(1) 生物多様性を社会に浸透させる 、(2)地域 における人と自然の関係を見直し・再構築す る、 (3)森・里・川・海のつながりを確保 する 、(4)地球規模の視野を持って行動す る、に加えて新たに(5)科学的基盤を強化し、 政策に結びつける、が位置づけられている。 以上のような動向を環境教育という視点 からみると、これまで進められてきた「持 続可能な開発のための教育の 10 年(DESD、 2005 〜 2014 年)」に生物多様性の視点が 加わることによってどのような変化が生まれ るかという問題がある。少なくとも、人間社 会の「世代間公正」と「世代内公正」を理念 としてきた持続可能性を、生物多様性をふま えた「生物種間公正」の視点を加えてあら ためて再構成する必要があるであろう。「生 物多様性基本法」(2008 年)は、その「目 的」として「生物多様性の保全」と「持続可
能な利用」の推進によって、「持続可能な社 会」の実現とあわせて地球環境の保全に寄 与することを挙げている。「生物多様性の保 全」と「持続可能な利用」は生物多様性条約 の目的を受けたものであるが、両者には、先 進国と途上国の対立だけではなく、自然(個 体・種・生態)の「保護 protection」か「保 存 preservation」か「保全 conservation」か
「賢い利用 wise use」かといった考え方の差 異、あるいは環境主義かエコロジズムか、さ らには自然主義か人間主義かといった環境思 想上の基本的対立も含まれおり2、生物多様 性について検討する際には、これらの対立を どう乗り越えて行くかということも問われて くるのである。
ここで、生物多様性基本法の目的には、生 物多様性条約にある「③遺伝資源の利用から 生ずる利益の公正で衡平な配分」が欠落して いることも指摘しておくべきであろう。それ が先進国と発展途上国の関係の固有の問題と して理解されたからであろうが、日本の立ち 位置を明確にした目的化が必要であったと言 える。より一般的には社会問題へのかかわり を避けたとも言えるが、人間社会に重点をお く「持続可能な発展」と自然生態系にかかわ る「生物多様性」の理解の間には埋められる べきギャップがあるのであり、それらの解決 に取り組むことなしには生物多様性基本法の 目的(「自然と共生する社会の実現」)は達成 されないであろう。
「共生」概念はアジアとくに日本起源の概念 であるが、21 世紀の新しい環境思想となり うると考えられている3。もちろん、生物多 様性という視点に立った場合、「生物種間の 相互作用ネットワーク」という生態学的視点 からの「共生」理解は重要な前提である4。 しかし、自然と人間の共生は、人間同士の共 生があってはじめて実現するものだという理 解が必要となる5。すなわち、「自然と共生 する社会」を実現するためには、自然生態学
的な共生関係をふまえた上で、「自然—人間 関係」の問題を「人間—人間関係」の問題と 同時に解決していかなければならないのであ る。そして、両者の問題の解決に「人間の自 己関係」にかかわる教育実践をとおしてアプ ローチしようとするのが教育学の立場にほか ならない。
もちろん、すべての生物にとって環境への 対応は学習過程である。その意味では諸個体・ 個体群・種にとって「環境」が最大の「教師」 である。しかし、人間にとって最も影響があ る直接的な「教師」は人間自身(および人間 が作る教育的環境)であり、人間は諸個人や 諸集団を越える「類的存在」として、人類の あり方も考えることもできるようになってき た。人間が当面する課題を克服して行くため には、諸個人から人類に至る人間自身のあり 方にかかわる「自己関係としての教育」を変 革することが不可欠なのである。21 世紀の グローカルな基本問題は、「自然—人間関係」 にかかわる地球的環境問題と「人間—人間関 係」にかかわる社会的排除問題であるが、両 者を同時に解決して行く方向での「共生の教 育」が求められている。ここでは、より具体 的に、これらの同時的解決にグローカル(グ ローバルかつローカル)な視点から取り組む のが「持続可能で包容的な社会」をめざす実 践であり、「持続可能で包容的な地域づくり 教育(ESIC)」だという理解を前提にしてい る6。
本稿は、教育学・環境教育論の立場から生 物多様性を考える前提として、「多様性」概 念を生物種や生態系の枠内だけにとどめず、 人間とその社会のあり方にまで広げ、とりわ け学習や教育にかかわる概念として位置づけ て行くための課題を明らかにしようとしてい る。最近では、国際性と市民性をもって計画 的に環境改善の実行力を求めるような<環境 教育>に対して、社会のあり方と人間存在の あり方を深く問う教育としての「環境教育」、
環境持続性・社会的公正に加えて「存在の豊 かさ」をエコロジカルな課題とするような環 境教育学も提起されている7。生物多様性を 切り口に環境教育を考えることは、そうし た存在論的次元をもふまえつつ、「共に生き ること」を考える環境教育学の創造にもつな がっていくであろう。
なお、「生物多様性」の理解は多様であり 得、これまでに、生物の「豊かさ」や「関係 性」に着目したものなどがある8。ここでは、 出発点として「生物多様性条約」の定義を前 提にして議論をすすめていく。同条約では、
「すべての生物の間の変異性」を「生物多様性」 と言い、多様性には①種内(遺伝子)の多様 性、②種間の多様性、③生態系の多様性とい う3つのレベルがあるとしている。日本の生 物多様性基本法では、生物多様性とは「様々 な生態系が存在すること並びに生物の種間及 び種内に様々な差異が存在すること」と定義 されており、生物多様性条約の定義が踏襲さ れていると言える9。
以下、まず 1 で、生物学的理解とは区別 される環境「教育学」の側から、生物「多様 性」と「自然との共生」にかかわる教育実践 をどのように位置づけるべきかについて述べ る。次いで2では、とくに「生態系」レベル での多様性を理解する際の課題を、進化論— 生態学的視点にたって比較環境倫理学を展開 するキャリコットの提起を手がかりに検討す る。そこでは土地倫理や風土論、COP10 で 推進課題とされている「SATOYAMA」等に ふれることになろう。そして3では、「生物 多様性条約」をめぐる議論において、先進諸 国や国際機関で主流となった E.O. ウィルソ ン的な生物多様性論に対して、「第三世界ネッ トワーク」の立場から、生物多様性を否定す る「モノカルチャー化」への批判を展開した V. シヴァの主張を検討して、そこから生ま れる今日的課題を考える。シヴァは、生産・ 生活様式としての「地域農業生態系」の理解
を基本にし、そこから経済・デモクラシー・ 文化にわたる「アース・デモクラシー」を提 起した。そこで4ではさらに、社会的承認関 係拡充の視点から生物多様性をどう位置づけ るかについて検討する。そこでは「生態サー ビス」論の批判的検討と同時に、「相互承認」 を不可欠のものとする教育実践の再評価・拡 充が必要となるであろう。
以上をふまえて5では、「教育モノカル チャー」を克服して、学習と教育の「多様性」 を担保する地域環境教育実践の展開構造を提 示し、最後に6で、その中核となる「地域環 境創造教育」の位置づけと展開可能性につい てふれる。
1 多様性=個性を育てる「自然との共生」 と教育
既述のように「愛知目標」では、20 の「個 別目標 Target」を挙げたが、2020 年まで の「短期目標 Mission」として「生物多様性 の損失を止めるための効果的かつ緊急な行 動」を提起しつつ、2050 年に向けた「長期 目標 Vision」として「自然と共生する Living in harmony with nature」世界を掲げている。 つまり、生物多様性の問題に取り組む目的は
「自然と共生する社会」の実現であり、その ことは「生物多様性基本法」の「目的」にも 明記されている。「生物多様性の保全と持続 可能な利用」をバランスよく(「生物の多様 性に及ぼす影響が回避され又は最小となるよ う」)推進するということは、そのための「基 本原則」とされているのである。それゆえ、 まず問われるのは「共生」の実践と論理にお ける「多様性」の意味付けである。
生物の多様性を理解するということは、ま ず、それぞれの間の「差異(変異性)」、ひい ては個々の生態系、種、集団、そして個体の
「個性」を理解するということである。その ことは、人間がその「個性」を認識し、一定
の意味あるものとして捉える能力を前提にす る。その際に基本となるのは、一定の生息地・ 生息環境にある、生きた「個体ないし個体群」 である。
もちろん、それは生態系とその展開をアト ミズム(個体還元主義)的にみるということ ではない。個体変異を前提として自然淘汰(性 淘汰を含む)による進化を説明したダーウィ ン、とくに突然変異と生存競争を重視するネ オ・ダーウィニストたちはアトミズム的傾向 をもち、しばしばその通俗化された反面とし て全体主義=優生主義あるいは社会ダーウィ ニズムに反転する。それらをホーリズムの立 場から批判した今西錦司は、種を生物全体社 会の部分社会と捉え、その構成単位として個 体を考えた上で、個体の「二面性」理解を提 起した。すなわち、棲み分けを固めるために は個体に「甲乙なし」という共通性が、社会 組織を固めるためには「甲乙あり」という個 体差が必要となるのであり、「種と個体とは 二にして一のもの」であるという個体理解の 重要性を強調した10。棲み分け、種社会(「個 体群」を超えて種の個体全体を含んだリアル な存在)とその分化、あるいは種の自己完結 性と並行=定向進化といった独自の進化論を 展開した今西の仕事は、このような個体理解 の上に展開されたのである。2で述べる種と 個体、生態系と種の関係における「一と多の 弁証法」は、こうした理解を出発点として個 体・種・生態系を歴史的・社会的・現実的に 理解することによって、アトミズムとホーリ ズムへの分裂=振動を乗り越えようとするも のである。
ところで、生物多様性条約や生物多様性基 本法における「生物多様性」の理解では、種 内の差異を遺伝子的差異と同一視する傾向が ある。しかし、種内の差異=変異性を遺伝子 レベルで捉えることを優先するいわば「遺伝 子還元主義」あるいは遺伝子の本質とされる 情報を重視する「情報主義」は、生物個体が
もつ全体性、その歴史的・動態的形成過程を 捉えることはできない。
周知の「利己的遺伝子」(R. ドーキンス) 論や遺伝子操作的技術論の問題点は別にして も、ここでは、生物多様性の保全という視点 から、遺伝子=情報化による環境問題解決へ の主張についてふれておくべきかも知れな い。たとえば、遺伝子—人間脳の「DNA メタ・ ネットワーク」から、人間脳—コンピュータ の「ミーム(文化的遺伝子)・メタ・ネットワー ク」への発展を提起する佐倉統や、現代の「消 費化革命」と「情報化革命」が環境問題を解 決する世界を切り開くという見田宗介である
11。これらはいわゆる「ハイテク汚染」「IT 汚染」(吉田文和)といった技術的問題や「情 報化」がもたらす社会構造的諸問題を考慮し ていないというだけでなく、遺伝子や情報の レベルでは捉えられない「個体」の全体性や その成長過程、したがって学習や教育実践の あり方をふまえない楽観的未来社会論であっ たと言える。われわれはさらに、「情報基盤 社会」という 21 世紀社会論の実態、生物多 様性保全に大きな影をもたらしている「知的 財産」や「特許権」の問題もふまえて検討し て行かなければならないであろう。
そもそも「利己的遺伝子」論などが前提に した遺伝子理解は、いわば「メンデル段階」 のものであった。生命科学者・中村桂子は、 遺伝子から DNA へ、そして DNA の総体を扱 うゲノムの研究へという展開をふまえて、「自 己創出する生命」という理解の重要性を指摘 している。それは自然・人・人工の世界を統 合しつつ、「自分も入り込んだ自然、真の自然」 を理解する「生命誌」として知の体系化をは かろうとするものである12。ゲノムをのぞき 窓にして、「普遍性—自己創出(自己組織化)— 多様性」という枠組みで「生命」を捉えよう とする中村の提起は、「一と多」、「普遍性と 多様性=個別性」の二元的対立を「自己創出 する生命」を媒介に止揚する方向性を示して
いる。それは生物多様性にかかわる教育学・ 環境教育学においても参考となる提起であっ たと言える。教育学においても「普遍性と多 様性」の対立は基本的なものであったからで ある。
遺伝子・DNA 決定論が生物学的にみて問 題なのは、ゲノムは DNA によって合目的的 に構築されたものではなく、遺伝子レベルで すらも冗長性・多義性、「あいまい性」をもっ ていること、そこから個体=「自己」が生成 してくるダイナミックな過程を説明できない からである。免疫学者の多田富雄は、その過 程を説明すべく、自己複製だけでなく、多様 化や自己適応、自己組織化などにより、自分 を構成する諸要素とそれらの関係までを動的 に発展させて、「自己」を自ら作り出してゆ く「超(スーパー)システム」論を提起して いる。そして、この自己言及的・自己決定的 な性格をもつ「超システム」の論理は、人間 の社会・文化・心のあり方にもみられるので はないかと言う13。それは、人間の学習活動 の特質をふまえつつ、「人間の自己関係」と しての教育実践、諸個人の自己教育活動を援 助・組織化することを課題とする教育実践を 理解しようとする教育学にとっても重要な提 起であったと言える。
しかし、教育学のアプローチは遺伝子学や 免疫学のそれと同じではない。教育学的視点 から「多様性」の意味を理解するためには、 まず、自己言及的・自己決定的な「個体性」 を理解して行くプロセスをふまえておくこと が重要である。遺伝子の変異=差異とその発 現に還元されない「個体性」、その生成・発達・ 消滅の過程こそが、教育実践がかかわる基本 的過程であるからである。
人間が「生きもの」の個性を捉えるのは、 みずからと他者を個性あるものとして理解で きることを意味する。前提としては、自然界 においても多くの動物は、大きさや姿形、に おいや音声によって互いに個体識別をし、な
わばりや種社会における位置などを通して、 それぞれ個性をもって生きているということ がある。しかし、多くの場合、人間はそうし たことを知らなくとも、人間を擬して他の生 物種・個体の固有性を捉えているのである。 それは、ペットから動物園の動物、あるいは 家畜に名前=固有名詞を付けるといったとこ ろに現れている。生物多様性の理解を深める ということは、人間という生物種の独自性や 多様性を理解する能力と相即的であると言え る。
生物の個性を理解する方法は、当初は比較 と類型化という博物学的手法を基本としてい たが、19 世紀における進化論の登場により、 それらが個体差を前提とした自然史的過程を とおして生まれてきたものと理解されるよう になった。そして生態学は、個性的な個体や 種が相互に不可分の関連のもとにあることを 明らかにした。こうして今日、生物多様性は この進化論=生態学的理解を前提にして理解 されなければならなくなっていると言える。 それは、中村の言う自然・人・人工の世界を 統合、すなわち、「環境を含む人間」と「人 間を含む環境」を統一的に理解する上でも不 可欠の前提である。
第二次大戦後の生物学では、遺伝子の固有 性を前提とし、個体あるいは集団や種が、生 誕から死にいたる過程で遭遇する環境(これ も個性的なもの)に依存するものとして理解 されてきた。生物社会学は一定の階層性と構 造をもった「種社会」の中で生きる個体の個 性を捉えた。とくに日本発で展開した「霊長 類学」(「サル学」)は、餌付けによる精密観察、 共感法、世代を越える長期研究とともに「個 体識別の方法」によって、サル社会の構造と 人間への進化の独自性を明らかにする方向を 示した。そこでは、個と社会の不可分の関係 を、動物にも人間にも見ることができる14。 もちろん、人間にとって大きな意味をもつ のは、生物学的遺伝子以上に、とくに「教育」
を通した世代間・世代内での「文化的遺伝・ 伝達」である。「個体発生は系統発生を繰り 返す」という理解を前提にして、「生物学的 早産」(ポルトマン)、集団・家族の形成、そ こにおける「教育」の成立は、教育理解を捉 え直す原点として、最近の人間進化論や動物 生態論などの研究諸成果を生かしつつ、つね に反省的見直しをすることが求められる。 遺伝と環境の関係は、人間が諸個人の「性 格」を理解する仕方に重なっており、性格形 成にかかわる教育学が子どもを理解する基本 的枠組みであった。そのことはさらに、人間 の成長の過程は、それぞれ固有の可能性=「潜 在性 capability」をもった子どもが、環境と のかかわりの中で、あるいは教育的働きかけ を通して「発達 development」していく過程 に注目するという、近現代に支配的な教育学 的思想につながっていった。個性とその多様 性を理解することは、教育学の本質的理解に かかわることなのである。
一般に、「画一的教育」あるいは一面的な
「普遍主義的教育」によっては、個性と多様 性を実質的に理解するようなことはできない と言える。近現代の教育は、法の下での平等 を前提として、実質的な平等を実現するため に社会権として位置づけられてきたのである が、その前提は「個人の尊厳」である(日本 国憲法では、第 13 条と第 26 条の関係)。教 育学では尊厳を持った個人を「人格」とし、「人 格の完成(なしし全面的発達)」を教育の目 的としてきた。人格は実体・本質・主体の3 つの規定をもつが、「実体としての人格」の 前提になるのが「個体性」をもった人間諸個 人である。その理解において重要なことは、 固有性・総体性・可能性(潜在性)の理解で ある。それゆえ、個人を尊重するということ は、固有な差異を認める「多様性」を重視す るということである。諸個人の個性(アイデ ンティティ)は、諸個人の自己実現と相互承 認の実践、それらを促進する自己教育と相互
教育によって発展する15。
具体的に地域で展開されている環境教育の 全体をどう捉えるかについては5で述べる が、大きく、人間主義的な生活環境教育、自 然主義的な自然教育、両者を統一する環境創 造教育に分けることができる。人間主義的環 境理解を突き詰めると、人間による「環境支 配」の原因とされる「人間社会における支配・ 抑圧関係」の克服をめざす「環境正義」を強 調するソーシャル・エコロジーとなり、人間 同士の対等な「共生関係」、ひいては「相互 承認」を重視することになる。他方、自然主 義的環境理解を徹底しようとするディープ・ エコロジー運動はしばしば人間的自由を否定 する教条的なものとして理解されたりする が、同運動を提唱した A. ネスは、人間的諸 能力の本質的発展としての、拡大された「自 己実現」を提起していた。そこでは、「主体・ 客体・媒体の3つの要素が相互に作用し合う という状況」が生まれ、自己が広がり深まっ て、「他者の中に自分を見る」あるいは「み ずから生き、他者を生かす」ことが原則にな ると言う16。
自己が広がり深まるということは、同じ人 間としての他者ばかりでなく、自然としての 他者を「非有機的身体」として理解し、その ことをふまえて、「人間主義と自然主義を統 一」(K. マルクス)していくことへとつなが ることになるであろう17。実践的には、ほん らい自己実現は相互承認と不可分のものであ り、自然主義と人間主義を統一しようとする 環境創造教育の実践においては、両者の相互 豊穣的的発展がはかられなければならない。 自己実現活動を通して獲得される「拡大さ れた自己」は、「自我」はもちろん、倫理的 自己や社会的自己をも超えて、存在論的に理 解された「エコロジー的自己」である。それは、 筆者の言う「実体としての人格」の理解にか かわる。そこでは、これまでの科学的認識の みならず、生活的・実践的論理をふまえるこ
とが必要であり、しばしば身体的・文学的・ 芸術的あるいは祭礼的・神話的・宗教的等の 表現活動をとおした理解が求められる。とく に具体的な教育実践においてはそのことが充 分にふまえられなければならない。教育学的 に重要なことは、ネスが「媒介」としたもの を人間的行為=実践として捉え直し、「自己— 行為—対象—人間関係」の総体にかかわる学 習とそれを援助・組織化する教育実践を位置 づけることである18。それらの諸実践の全体 をとおして諸個人の自己実現と相互承認を発 展させるべく、環境・エコロジーにかかわる 自己教育・相互教育活動を援助・組織化する のが環境教育実践の基本的課題となる。それ は、かかわる諸人格の「個性」を豊かにし、「多 様性と総合性」の理解を深めることになるで あろう。
もちろん、「個性」や「多様性と総合性」 を重視する教育が、これまでの実践の場で全 面的に展開されてきたわけではない。日本に おけるいわゆる受験主義的・画一的・管理主 義的と呼ばれるような教育は、「個性と多様 性」の教育を押しつぶす側面があった。これ らを反省した「ゆとり教育」や「個性の教育」 を重視した 1980 年代末葉からの政策動向も あったが、学力の国際競争への対応が政策的 課題とされた 21 世紀になってからは逆流が おこっている。能力主義的な競争(「生存競争」 と「自然淘汰」)が、個体差を前提・強調す るように見えながら、結局は、大多数の「個 性と多様性」を否定するということになりが ちだということは、ひとつの重要な教訓であ る。
しかし、こうした中であれ、学習者の自己 教育・相互教育をとおして自己教育主体へと いう、現場での教育本来の努力は多様に試み られてきた。たとえば、学校環境教育では「総 合的学習」として取り組まれてきた諸実践が あるが、とくに地域と結ぶ環境教育の実践の 中から「個性と多様性」を重視することの上
に「協同的活動主体形成」をめざす環境教育 が生まれてきたことなどは注目される19。そ れらにおいては、問題の意識化にとどまらず、 それを自分の問題として考える「自己意識化」
=自己の拡充が位置づけられており、そこか らかかわる他者との協同によって「自然と共 生する社会」のあり方を考えるという実践が 共通にみられる。それは、自己と他者の個性 を理解することを意味するが、そうした実践 は「環境」の理解においても、社会教育を含 めた教育そのものの展開においても不可欠の プロセスなのである20。
生物多様性と直接関わるのは、COP10 で 推進課題(「SATOYAMA イニシアティヴ」) とされた「里山」(人間と自然の相互交渉に よって形成されたもの)を利用し、場とする 教育活動である。ここではさらに、しばしば レクレーション施設としてみられている動物 園と植物園などを環境教育施設として見直す ことの重要性を指摘しておきたい。動物園や 植物園が、「種」の保全・繁殖の役割をもっ ているというからだけではない。それがほん らい博物館=社会教育施設であり、公共的活 動としての地域環境教育実践の出発点となる と考えられるからである。「施設教育」は戦 後社会教育の基本であっったが、その前提は、 自立した市民(子どもを含む)の形成であり、 その「学習の自由」を保障するものとして、 公共的な社会教育施設が位置づけられたので ある21。
とくに生物多様性にかかわる活動をしてい る動物園では、身近な動物から地球上のあ らゆる地域の希少な動物までを飼育してい る。それらはしばしば固有の愛称で呼ばれて おり、一定の種であると同時に「個」として 理解されている。そして、個々の動物の多様 な個性的特徴や能力を眼前にすることによっ て、「動物の側になって考える」「動物から教 えられる」可能性がある。とくに各動物園で 取り組まれてきている「行動展示」とそれに
伴う教育活動などによって、そうした機会は ひろがっている。動物から学ぶということは 同時に、人間みずからの生活を見直し、人間 らしい生き方を振り返ることを意味する。最 近提起されている「生息展示」や園地・周辺 生態を位置づけた地域的展開、そして世界各 地の動物生態にかかわる映像なども加えた教 育活動では、当該動物が生きている環境、あ るいは同種または異種の集団の中での動物の 生態が理解できるようになっている。この延 長線上に、より広く動物生態学や動物行動学 などの知見をも加えて、人間の進化論的理解 の促進が可能となってくるであろう。もちろ ん、そこに独自の教育的課題が生まれてくる。 一般に、生物多様性の理解においては、進 化論的視点が弱い。進化論自体に「自然淘 汰(生存競争)論」と「相互扶助論」の対立 もみられる。それらへの対応を含めつつ、動 物園を契機にした学習には、差異=個性をふ まえた進化や生態的多様性の意味、そして人 間の将来的発展課題を議論する大きな契機が あると言える。そうした学習は、ふりかえっ て、現代社会のあり方を批判的に捉え直すこ とにもなるであろう。もちろん、それは植物 を通した学びでも可能である22。したがって、 動物園だけでなく、植物園でも、さらには自 然誌(あるいは生命誌)博物館や「生物園」
23、そして、生物多様性のホットスポットと 言える里山・里海や湿地などで、より発展的 に考えることができるであろう。
自然理解は人間理解と関連し合っている。 R.F. ナッシュは、アメリカにおけるリベラル な人権=「自然権」思想に始まる環境倫理の 歴史的発展を、「自然の権利」論への展開・ 拡充過程として整理した。そこでは、自己— 家族—部族—地域—国家—人種—人類—動 物—植物—生物から生態系、さらに地球や宇 宙にまでひろがる倫理的共同体の進化が展望 されている。それは、イギリス貴族に限定さ れた「マグナ・カルタ」に始まる自然権が、
アメリカ入植者(独立宣言)—奴隷—女性— 先住民—労働者—黒人、そして自然にまで広 がって行く過程と並行していること、そして しばしば、公民権運動・フェミズム運動と動 物解放運動のように、直接的つながりがある ことが示されている24。ナッシュによれば、 今日の生命中心主義・環境倫理学は 20 世紀 末の自由主義思想の最前線である。「自然の 権利」そのものの解釈には議論があるとして も、こうした経過をふまえるならば、われわ れは 21 世紀における生物多様性論を、人間 社会における多様性の尊重・実現、それらに かかわる教育実践の展開論理と関連づけて理 解する必要があるであろう。ただし、そこで 求められているのはナッシュの言う「自由主 義思想」を超える実践論理である。
今日、市場主義的グローバリゼーションの もとでの大競争、その結果としての格差拡大 が「排除型社会」と呼ばれるような社会を生 み出している。「社会的排除問題」への対応 が喫緊の課題となっているが、その前提はい わゆるマイノリティを含めたすべての人間の 人権の保障にもとづく、多様性の尊重である。 それは現在、東日本大震災の被災地・被災住 民において明白な問題となっているが、これ まで社会的排除の状態にあった地域と地域住 民のすべてにおいて重要な実践的課題となっ ているのである。
とくに「社会的弱者」と言われてきた障害 者や病弱者、エスニック・マイノリティ、一 般的には、女性や高齢者、そして若者と子ど もの位置づけが重要になっている。彼・彼女 らへの「社会的包摂」や「ケア」が政策的課 題にもなってきている。そこでの実践的な姿 勢と論理は、生命全体におよぶ可能性をもっ ていると言える。それらはまた、社会保障や 税制・年金等の制度のあり方を含めて、「世 代間」と「世代内」の公正、それを実現す るための連帯のあり方を問うている。つま り、国際的にはブルントラント委員会報告
書(1987 年)にはじまり、「地球サミット」
(1992 年)以来、世界共通の課題として理 解されてきた「持続可能性 sustainability」を、 人間を含む生物の「個性と多様性」をふまえ たあらためて問い直すという課題につながっ ているのである。
こうした中で、教育学視点から問われてい るのは、社会的排除問題に取り組む諸実践で ある。とくに近代西欧的理解とは異なる自然 理解と自然とのつきあい方をしてきた諸民族 の自然観、中でも長い間排除されてきた「先 住民」の知恵などが 21 世紀の環境思想と環 境行動のあり方を考える上で重要な示唆を提 示していることは、よく知られるようになっ てきている。先進諸国でも深刻化してきてい る社会的排除問題への教育的アプローチから は、個性と多様性をもった諸人格の人権を尊 重する「包容的教育 Inclusive Education」が 重視されてきており、そこから「協同の教育」 の諸実践が生まれてきている。それらは「共 生のための教育」であると言ってよい。その 実践と論理の展開は、「自然と共生する社会」 を実現しようとする「生物多様性戦略」の進 め方にも大きく影響することになるであろ う。
もちろん、種間の共生と(ヒトという)種 内の共生には差異があることをふまえておか なければならない。共生関係はしかし、「個— 集団—共同体」関係を基盤にして、重層的に 展開されてはじめて地球レベルの生態系につ ながる。そして、それらのそれぞれと全体の 関連の中での人間の位置づけが問題となって きているのである。それは静態的なものでは なく、動態的な変化の中にあり、それゆえ人 間の進化論的理解を前提とする「人間発達」 の論理をふまえた理解を求めることになる。
2 生態的多様性と文化的多様性——「一 と多の弁証法」、またはグローカルな時代 に——
生物多様性にかかわる教育では、「自然と 共生する社会」を実現する態度と行動意欲を 醸成することが重視されている。その際にふ まえておくべきことは、生物的多様性は文化 的多様性と相即的であるということである。 それは、自然的環境と人間的社会・文化の 調和を重視する改良主義的な「環境主義」の 立場からのみ理解されることではない。「自 然との調和は、人間と人間の調和なしには達 成できない」というソーシャル・エコロジー の立場から「多様性の中の統一」を強調する M. ブクチンのような主張25からはもちろん、
「環境主義」やソーシャル・エコロジーから 批判されているディープ・エコロジーの立場 からも生まれてくる理解である。たとえばネ スは、多元性・多様性の価値を重視し、ブク チンと同様に「多様性の中の統一」を強調す る「エコソフィー」の思想と運動を展開した
26。三浦永光は、ネスのエコソフィーとブク チンのソーシャル・エコロジーの共通性(「多 様性の中の統一」、地域社会の重視など)を 指摘しているが、前者が生命圏という「共時 的関係」、後者が人間進化に至る「通時的関係」 から検討している点に差異があるとしている
27。「進化論=生態学的」アプローチは本来、 これらを統一することを課題とする。
ところで、「生物多様性は文化的多様性と 相即的である」と言う時には生物多様性を、 遺伝子および種の多様性をふまえつつも、主 として「生態系の多様性」の問題として考え ている。そして、生態的多様性こそ、人間が 実際生活においてかかわるものであり、それ を前提にしてはじめて種や遺伝子の多様性を 現実的に考えることができる。もちろん今日、 遺伝子工学などの発展による遺伝子の保存や 組み換えも可能になってきており、たとえば 最近の ES 細胞から iPS 細胞への研究展開は、 生命における「普遍性と特殊性・個体性」と の理解に新たな発展をもたらす可能性があ
る。しかし、新しい遺伝子の創造は生態系の 中でしかできない。個々の種も、動物園など で保存することは可能であるとしても、「生 きた種」は生態系の中ではじめて存在するの である。種多様性は、生きた生息地としての 生態系の多様性によって保存される28。 その際、生物多様性条約が生態系を「植物、 動物及び微生物の群衆とこれらを取り巻く非 生物的な環境が相互に作用して1つの機能的 な単位をなす動的な複合体」だとしているこ とを確認しておくことも悪くないであろう。 微生物はもとより「非生物的な環境」も含め て生態系としているのである。その意味では、 生物だけの関係を取り上げた生態系論は厳密 には一つの抽象なのである。最近では「有機 物循環論」29も提起されているが、非有機物 を含めた地質学的な多様性も前提とされなけ ればならないであろう。生物多様性条約では、 これに対して「生息地」という生きた対象は
「生物の個体もしくは個体群が自然に生息も しくは生育している場所又はその類型」だと されており、「場所」だけでなく「類型」を 加えているところには実在論的にみた不徹底 があるが、ここではじめて「個体」が登場し ていることに着目すべきである。
生物多様性条約が言う生態系=「1つの機 能的な単位をなす動的な複合体」という理解 は、生態系をサイバネティックスやシステム 論的に理解する方向にもつながる。しかし、 諸種の生物個体や個体群は「生きた主体」で ある。それらによって織りなされる「動的な 複合体」は、外部から因果関係を中心にして いわば機械論的に捉えるのではなく、それを 知覚・認知・意味付けをする「主体」をとお して生成する「環(境)世界 Umwelt」(ユ クスキュル)が相互関連をなして展開すると いう理解が求められてくる。「環世界」は、 主体と客体が交互に関係し合う「機能環」を なし、対位法的適合関係をもった交響曲の「総 譜」のようなものとして理解される。ユクス
キュルは、機械論的環境理解と「環世界」論 的理解の対立を、「構造か総譜か、機械的か 音楽的か、因果法則か意味法則か、物質に従 うのか感覚に従うのか」、さらには「合理的 なのか想像的なのか、論理的なのか魔術的な のか」と提示している30。
ユクスキュルが演劇的・音楽的比喩を通し て表現しなければならなかったように、「動 的複合体」としての生態系は、機能論や「(静 態的)構造論」あるいはシステム論を超えた 複雑性・多様性をもったものとして理解され なければならない。こうした理解の上で、ま ずふまえておかなければならないのは、地球 の個々の生態系は、多数で多様に、それぞれ は2つとないかたちで存在しているとうこと である。この生態系の中で生きるひとつの種 としての人間の生き方=文化は当然のことな がら、それぞれに個性的な生態系によって規 定される。しかし同時に、人間は他の種に比 すことができないくらいの影響力をその生態 系におよぼしている。それゆえ、生態系理解 が一面的であれば、人間の活動は「生態破 壊」をすることをまぬがれないのである。さ らに言えば、生態系との「対位法」的関係 を形成するためには、人間活動そのものを
(ユクスキュル的表現を使用すれば)「交響曲 symphony」的関係に、またはより現実的に、 プロセスの中で創造される即興的な民族音 楽、あるいはジャズ演奏的な関係に再構成す ることが必要となると言えるであろう。 人間が生態系を生態系として知るように なってきたのは、19 世紀後半の「生態学」 の成立以降であると言える。そして、地球全 体をひとつの生態として理解するようになる のは、さらに「地球生態学」が発展してくる 20 世紀後半からであり、一般に理解される ようになるのは、1970 年代以降、地球的環 境問題が意識されるようになってからだと言 える。こうした中で、生態系理解における「一 と多の弁証法」が問われるようになってきた
のである。
しかし、人間は近現代の生態学が成立する 以前から、一定の知と規範をもって生態系に かかわってきた。この「一定の知と規範」は 文化の核心をなすが、自然的環境としての生 態系へのかかわり方は、広い意味での「環境 倫理」ということができる。それらはしばし ば道徳的・宗教的世界解釈の一環として存在 してきた。
生態系の有機的全体性を強調するラディカ ルな生命中心主義者であると同時に比較環境 倫理学者である J.B. キャリコットは、環境倫 理はユダヤーキリスト教的伝統だけでなく、 南アジアのヒンドゥー教・ジャイナ教・仏教、 東アジアの老荘思想・儒教、日本の仏教、極 西のポロネシアやアメリカ先住民、あるいは 南米、そしてアフリカの民間信仰などにも見 られることを確認した上で、次のように言う。 すなわち、政府省庁などによって進められて いる「純粋に世俗的で非宗教的な計画」は、「伝 統的な世界観が秘めている環境倫理によって 支えられ、命を吹き込まれることがないかぎ り、効果はあがらないだろう」と。そして、 こうした多様な環境倫理のグローバルなネッ トワークの重要性を強調しながら、それらを 繋ぎ、統合された全体へと結びつける共通の 一本の糸こそ、多様性の中に統一と調和を構 築しようとする、ポスト・モダニズムの「進 化論—生態学的」環境倫理にほかならないと している31。
たしかに彼の主張は、1980 年代に流行し たポスト・モダニズムの一環に位置づけられ ることも可能である32。また、その後のグロー バリゼーション下の文化的帝国主義の展開、 あるいはそれに対するオリエンタリズムやカ ルチュラル・スタディー、そしていわゆる「普 遍主義と共同体主義」の論争に対する批判も 含んでいるとも言える。ここでは、より積極 的に、それらを含めたポスト・ポストモダン の論理につながる「グローカルな論理」33と
しての内発的発展論=「持続可能な発展」論 につながる方向に注目しておきたい。それは、
「多様性の中に統一と調和を構築」しようと する態度にあらわれていると言える。
キャリコットは、アルド・レオポルドの言 う「土地倫理」34(生物地域における生物共 同体の成員としての倫理)論をふまえつつ、 進化論—生態学的環境倫理は、「諸関係の中 に組み込まれ、そこに根ざした集団としての 人間にとっての自己利益」、すなわち、自己 を超え出て広がって行くような、エコロジー における「自己実現」を求めるものだと言う。 それは、近代の機械論的環境理解はもちろ ん、「賢明な自己利益」を追求する功利主義 的理解を超えるものだとされている35。既述 のネスの「拡大自己実現」論とあわせて、環 境倫理学的に生物とくに生態系の多様性を理 解し、多様性の保全を進めて行くためのひと つの方法として評価することができるであろ う。
しかし、キャリコットにおいては多様性の 倫理的理解と生態学的理解の間になおギャッ プがあると言わざるを得ない。人間と自然が 相互交渉するような実体を通して、両者を媒 介していく必要がある。その可能性は、オギュ スタン・ベルクが提起する存在論的な「風土」 理解に求めることができるであろう36。それ は、風土を人間存在のあり方とする日本の和 辻哲郎などの議論とも重なって、文化と生態 的自然の相互関係を、具体的な実体をとおし て理解することを可能とする。ただし、ベル クの高度に哲学的な議論をそのまま生態系の 多様性を具現化するものとしての風土に適用 することはできない。
ここでは、亀山純生の風土理解を挙げてお こう。彼は、風土が注目される実践的理由と して、①環境の要素還元主義、②環境の「絵 画化」、③生態系保全、外来種問題、④自然 の歴史性・文化性と自然変容の限界、⑤あり ふれた自然保護の論拠、⑥自然と共生関係の
モデルの必要、の6つをあげている。とくに
③は、「地域の多様な生物が共存可能な生態 系ないし生態系システム」が問われるもので、 生態系の多様性に直接かかわる問題である。
⑥は、風土が自然と人間を統一的に捉える新 しい環境思想の実体的基盤となることを意味 している。
これらをふまえて亀山は、人間を、根源的 には自然に依存しつつ、「共同関係において 存在する文化的な身体的主体」と理解した上 で、「風土 Landschaft とは一般的には、一定 の地理的空間における共同社会と生活的自然 との一体的関わりの全体である」と定義する。 そして、風土の構造を、「俯瞰の3次元」す なわち生活様式(伝統)、空間(景観)、時間
(歴史)と、「関わりの3次元」すなわち技術 的関わり、象徴的関わり、社会的関わり、の 関連において捉えることを提起している。そ して、そうした風土理解による環境倫理にも とづいて、生態系の多様性については、①人 間存続の不可欠な前提的土台、②地域ごとの 人間と自然の関わりの相違による差異、③耕 地・里山のように、生物的多様性は自然への 関わりの豊かさに依存すること、④品種改良 や外来種導入は、地域生態系の固有の安定構 造の中に埋め込まれるべきこと、⑤「移入種」 も同様で、風土的関わりの保全の観点から考 えられるべきこと、を指摘している。亀山は 風土論が、「地域にねざすグローカルな環境 倫理」の論点を提供すると同時に、人間疎外 の克服の課題への具体的アプローチになると いう意味で、「環境倫理と環境教育を接合す る理論的枠組み」の提起にもなるとしている
37。
ここにわれわれが風土に注目しなければな らない理由があると言える。風土を考えるよ り具体的な対象としては、I. イリッチが提起 したような多様なコモンズ(共有資産)、日 本の脈絡では、たとえば里地・里山・里海が 考えられる。里地・里山・里海は、人里と奥
山・遠海とを媒介する位置にあり、まさに人 間社会と自然の共生を象徴する場である。日 本の「第3次生物多様性国家戦略」(2007 年) では、生物多様性の3つ危機として、人間活 動・開発の負の影響、外部から持ち込まれた 外来種・化学物質などとともに、「自然に対 する人間の働きかけが減ることによる影響」 が挙げられた。そして、4つの基本戦略とし て、①生物多様性を社会に浸透させる、②地 域における人と自然の関係を再構築する、③ 森・里・川・海のつながりを確保する、④地 球規模の視野をもって行動する、が掲げられ た。生物多様性の保全に向け、多様な動植物 の生息地である各地域の里地・里山・里海を 中心とする風土の実践的重要性が意識されて きたと言える。
COP10(2010 年 ) で は「SATOYAMA イ ニッシャティブ」を推進することが重要課題 とされ、日本の沿岸における豊かな生物多様 性も注目された。風土は、これらの相互関 連を含んだ「流域」を単位として考えられ るであろう。流域を単位として考えること は、東日本大震災後の防災・保全計画を考え る際にも重要な課題となってきている38。生 物多様性と文化的多様性を同時に問うような Nature-culture Complex としての「生態学的 な地域構造論」39も提起され、それらは後述 の「バイオリージョン」の考え方につながっ ている。
もちろん、ここまで議論してくると、生態 の多様性を環境倫理の視点から捉えることの 限界もふまえておかなければならない。たと えば、『銃・病原菌・鉄』で比較文明論的視 点から、大陸によって社会発展の速度が異な ることを明らかにしたダイアモンドは、同じ く比較研究法によって、とくに環境問題に焦 点をあて、社会崩壊の要因を探っている40。 その結果、潜在的な要因として①環境被害、
②気候変動、③近隣の敵対集団、④友好的な 取引相手、そして⑤環境問題への社会の対応
の5つを挙げている。具体的な環境問題とし ては、(生物多様性にかかわる)自然の生息 環境の破壊のほか、近年深刻化してきたエネ ルギー・光合成の限界・有毒化学物質・大気 の変動、天然資源の破壊・枯渇・限界、有毒 物質、そして人口の問題を指摘している。し かし、これらは相互に関連しあっている。そ うした中で、潜在要因の⑤にかかわって、環 境被害に結びつく(宗教を含む)「価値観」 を重視し、今日的問題としては、政治的理念 と大企業の「(環境的)公共性」理解を問題 にしている。そして、「長期的思考を実践す る勇気」さえあれば、問題は深刻であっても 解決不能ではなく、環境保護思想が一般に広 まり、グローバル化による連結性が高まって きている動向をふまえて、みずからは「慎重 な楽観主義者」であると結論づけている。基 本的価値観や政策理念まで含めた「環境倫理」 を実践することの重要性が指摘されていると 言える。それは、生物多様性に即しても同様 であろう。
COP10 においては、民間参画と地域戦略 が重要視され、生物多様性国際自治体会議も 開催され「地方自治体と生物多様性に関す る愛知・名古屋宣言」も採択された。千葉 県・埼玉県・兵庫県をはじめ、日本における
「生物多様性地域戦略」策定も進んでいる41。 2011 年には「生物多様性自治体ネットワー ク」が設立され、2012 年 6 月現在で 123 自治体が参加している。これまでに進められ てきた自治体環境計画を含め、これらの生物 多様性地域戦略の展開が、上述のような理解 をふまえて実践的に展開しうるかどうかが現 実的な課題となってきたと言える。
キャリコットは、倫理学はほんらい最も直 接的に実践にかかわる分野だとしており、最 終章でかかわる諸実践を紹介していることが 注目される42。
ユダヤ—キリスト教的伝統からは「番人の 環境倫理」にもとづいて、土壌浸食につなが
らない総合的な農業方法を普及している「番 人の農業計画」、とくに農家の実践交流・学 習組織としての「持続可能な農業協会」や「持 続可能な農作業グループ」の活動が紹介され ている。そこでは、多様性を強調しながら、 すべての農場を「農業生態系」とすることを 目指している。ヒンドゥー教の環境倫理の実 践としては、ガンディーの思想を背景にし て、身体をはった森林保全運動の展開で著名 な「チプコ運動」(3でふれるシヴァも参加 している)が挙げられている。そこではディー プ・エコロジー的あるいはフェミニズム的運 動と、「村の自治のためのダショーリ協会」 の活動など、公正で持続可能な開発を目標と する実践があることが指摘されている。そし て、仏教にもとづく実践事例としては、タイ の森林保全活動とともに、「中道」を重視す るスリランカの「サルボーダヤ運動」が紹介 されている。そこでは、「資源の管理権と技 術を地域住民の手に移す」ような内発的開発、 とくに「適正技術」(E.F. シューマッハー、「中 間技術」とも呼ばれる)による持続可能な開 発が推進されていた。
ただし、これらの諸実践を「持続可能な発 展のための教育(ESD)」として、実践論的 に理論化することは環境教育学固有の課題で ある。その課題に取り組むためには、地域住 民主体の環境保全運動にかかわる学習活動の 展開論理を位置づけて ESD の革新をはかる ことが必要である。比較倫理学的検討に終始 するキャリコットはこの課題に応えておら ず、残されたものとなっている。
3 生物多様性と農業生態系(生産と生活 の多様性)——モノカルチャー化を超え て——
人間は外的自然との物質代謝を通して存在 している。具体的には、生産・消費(生命と 生活の再生産)を通してである。したがって、
生物多様性はこの物質代射過程の多様性を保 障するものでなければ、現実のものとはなら ない。人間と外的自然との物質代射過程を直 接的に行うのは、いわゆる第一次産業であり、 とくに「農業(林業・漁業を含む)生態系」 の多様性が問われることになる。
「愛知目標」では目標4「持続可能な生産・ 消費計画の実施」が挙げられ、具体的には目 標7「農業・養殖業・林業の持続可能な管理」 や目標 13「作物・家畜の遺伝子の多様性の 維持・損失の最小化」が挙げられている。後 者は、生物多様性条約(1992)の目的のう ちの「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正 で衡平な配分」にかかわる課題でもある。 生物多様性条約(1992 年)は、グローバ ルな視点から生物多様性に対する規制を設け ようとするものであり、原則として、「自国 の資源をその環境政策にしたがって開発する 主権的権利を有し、また、自国の管轄又は管 理の下における活動が他国の環境又はいずれ の国の管轄にも属さない区域の環境を害さな いことを確保する責任を有する」(第3条) としている。そこには、多国籍バイオロジー 産業をもつ先進諸国と、生物多様性が主とし て存在しながらそこから受益できていない第 三世界の諸国との対立が反映している。「第 三世界ネットワーク」の重要な理論家=実践 家であった V. シヴァは、この条約の次のよ うな欠陥を指摘している43。
第1に、国家間の問題として処理されてい て、実際に生物多様性を保全・維持している
「ローカルな共同体(コミュニティ)の主権」 が欠落していることである。この結果、生物 多様性の保護のための条約が「生物多様性の 開発のための条約」に歪められる恐れがある。 第2に、バイオテクノロジーが生物多様性の 保全と持続可能な利用のために不可欠だとい う想定(第 16 条第1項)があるということ である。それは、生物多様性が商業的なバイ オテクノロジーのための「単なる原材料」と
なり、遺伝的に均一なバイオテクノロジー製 品によって駆逐されてしまうことを意味して いる。第3に、生物資源に関する特許と知的 所有権を容認していることである。そのこと が、先進諸国と多国籍企業の利益になること は言うまでもない。第4に、これまでの「作 物遺伝子銀行」(所在地は先進国)の所有権 と諸権利の規制対象からの除外である。この 一方で、「インフォーマルな技術革新の担い 手」が保障を受ける権利は認知されていない。 第5に、「遺伝資源の原産国」「生息域内状況」
「生態系」などが、先進国の利益に合致する 都合の良い解釈ができるように定義されたと いうことである。それらは、形式には「対等 の権利」という前提のもとであるが、そのこ とは実質的に先進国の利益になる。第6に、 当座の財政的メカニズムとして、世界銀行の
「地球環境ファシリティ」を容認しているこ とである。第三世界からの提案(「生物多様 性基金」)は削除された。
以上のような欠陥を指摘しつつもシヴァ は、第 14 条(影響の評価及び悪影響の最小化) にみられる「バイオセーフティ」の考え方な どを発展させていくような「条約の修正と適 正な解釈を実現する必要」を指摘している。 そして、第三世界にとっては生物多様性の保 護者であった「民衆の保護」を基盤とし、「生 きている生物多様性と生きている共同体のあ いだのパートナーシップ」こそが保全される べきだとしている。
このようなシヴァの理解は、国際開発を進 めてきた先進諸国や国際的諸機関の理解はも とより、「バイオフィリア」や「深遠な自然 保護倫理 deep conservation ethic」の提唱者 であり、生物多様性の危機を早くから指摘し てきた研究者として知られる E.O. ウィルソ ンの、生物多様性条約成立時における次のよ うな提案と比較してもラディカルなものであ ると言える。すなわち、彼は「人類に対する コストを最小限にしつつ、生物多様性の損失
を最小限に押さえて」危機を乗り切るために は、これまでよりはるかに「長い時間に基づ いた知識と実践的倫理」(彼は、2でみたキャ リコットと同様、「環境問題とは本質的に倫 理の問題」だと言う)をふまえた総合的研究 が必要だとした上で、次のような提案をす る44。①世界の動植物相調査(とくに生物多 様性のホットスポット)、②生物的富の創造、
③持続可能な開発の推進、④生き残っている ものの救済、⑤原野の復旧、である。彼は「強 力な法律の力と国際協定」を強く求めている が、その提案には生物工学・生物経済学や「種 子銀行」、「環境スワップ」、そして科学的森 林管理や人口政策など、議論が分かれ、シヴァ が強く批判するような諸点が含まれている。 シヴァの主張の背景には、生態系・生命形 態・共同体の生活様式は「共進化」の関係に あり、「文化の多様性と生物学的多様性は連 動」しているという基本理解がある。しかる に、国際的開発プロジェクトや、「緑の革命」
(農業)・「白の革命」(酪農)・「青の革命」(漁 業)といった「革命」は、生物的均質性とモ ノカルチャー化を押し進め、生物多様性を危 機に陥れてきた。移住させられたり、生活・ 生産基盤を奪われたりした人々が生物多様性 を破壊するのは二次的な効果にすぎない。バ イオテクノロジー産業と国際開発によって進 められるモノカルチャー化(画一化)は、① 生態学的な不安定性、②地域住民の暮らしの 排除をもたらす外部からのコントロール、③ 一次元的枠組みによる効率、を進める「生物 帝国主義」と言うべきものである。これを、「あ らゆる生命形態の固有の価値と、その固有の 生存権」、そして「ローカルな生物多様性と 共進化してきた共同体の本来の貢献と権利」 にもとづく「生物民主主義 biodemocracy」 に置き換えて行かなければならない、とシ ヴァは言う45。
彼女はその後、こうした理解を拡充して、 生命中心の経済・民主主義・文化である「アー
ス・デモクラシー」、すなわち「大地の市民 による民主主義」を提起する。「あらゆる生 物種、民族、文化は、それぞれ固有の価値を もっている」から始まるその原則は、①あら ゆる生命にとって民主的であること、②自然 および文化の多様性の保護、③自然権として の「生命を持続させる権利」、④生命中心の 経済民主主義、⑤ローカル経済基盤、⑥生命 中心の民主主義と文化、⑦平和と配慮と共感 のグローバル化、といったものである46。こ れらの体系化は残された課題となっている。 ディープ・エコロジー運動や生命中心主義的 環境倫理論、とくにエコ・フェミニズムや
「アース・ファースト!」運動などとの立ち 入った区別と関連づけも必要であろう。実践 論レベルでは、アース・デモクラシーの諸実 践も紹介されているが、それらの理論化も必 要である。しかし、これまでのところで、本 稿の課題とのかかわりにおいて重要な点を確 認するならば、以下のとおりである。
第1に、多様性に対する「モノカルチャー」 という批判の視点の発展である。それは、直 接的には作目・樹目・畜種・品種・魚種の「画 一性」を意味するが、その影響は生産手段や 労働力のあり方、そして労働の仕方そのもの にまで及ぶことになる。日本の農業の場合で も、高度経済成長期における商業的作物へ の「選択的拡大」から始まり、「稲作モノカ ルチャー化」が問題とされたが、それは機械 化・化学化農業の展開と並行したものであっ た。もちろん、水田のもっている環境保全的 機能は正当に評価しつつも、シヴァが問題視 する「農業の工業化」や、「加工型畜産」の 問題を含めて考える必要があろう。今日、農 業の基本に立ち返った農業生産のあり方が問 われ、そこから現代の農業・食料問題ととも に、「持続可能な生産力」の課題が提起され ている47。
そうした課題に取り組むためには、ひろく 農業の文化・文明論的あるいは哲学的な考察