初級段階の中国語学習者の意欲向上を目的とする授業法の開発とその実践報告—教養語学を中心に
20
0
0
全文
図

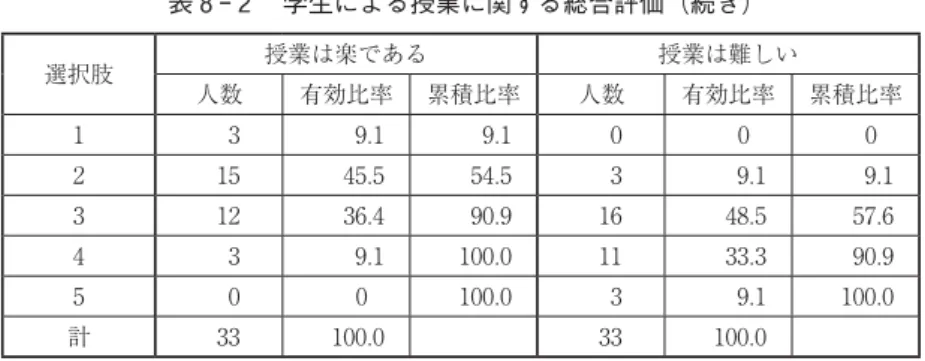
関連したドキュメント
工学部の川西琢也助教授が「米 国におけるファカルティディベ ロップメントと遠隔地 学習の実 態」について,また医学系研究科
実習と共に教材教具論のような実践的分野の重要性は高い。教材開発という実践的な形で、教員養
英語の関学の伝統を継承するのが「子どもと英 語」です。初等教育における英語教育に対応でき
C :はい。榎本先生、てるちゃんって実践神学を教えていたんだけど、授
を育成することを使命としており、その実現に向けて、すべての学生が卒業時に学部の区別なく共通に
を育成することを使命としており、その実現に向けて、すべての学生が卒業時に学部の区別なく共通に
● 生徒のキリスト教に関する理解の向上を目的とした活動を今年度も引き続き
活用のエキスパート教員による学力向上を意 図した授業設計・学習環境設計,日本教育工